Knowledge
エンジニアが語る、ダイナトレックで働く面白さ。 ーお客さまの近くで開発できるからこそ、ユーザーにとっての“最善”が実現できるー


1980年代から官公庁や金融機関、公共インフラ企業などの大規模顧客向けにシステム開発・コンサルティングを行うダイナトレック。現在は、顧客が抱えるレガシーシステムの課題に対し、独自の仮想統合技術を持つ自社プロダクトDYNATREKによって全社横断的なデータ活用を支援しています。今回は、ダイナトレックのエンジニアチームに、顧客の声を反映したプロダクト開発の裏側、そして、ダイナトレックならではのコンサルティングとプロダクト開発の楽しさを聞きました。

右から取締役の佐伯、プロダクト開発部の櫻木、コンサルティング部の小川
顧客のすぐ隣で開発するから、喜ぶ顔を目の当たりにできる
―エンジニアチームの櫻木さんと小川さんのご経歴をおしえてください。
櫻木:私は大学時代、工学部で核融合のシミュレーションをしていて、そこでコンピューターやプログラミングと出会いました。その後、IT企業を経てダイナトレックに入社。今はDYNATREKの製品開発に携わっています。
小川:私は、テレビ局のシステム管理を10年ほど経験し、営業やスポーツ部門を経て、2年前にダイナトレックに入社しました。

―今はどのようなお仕事をされていますか?
櫻木:私は長くお客様へのコンサルティング業務に携わっていますが、軸足としてはプロダクトの設計・開発に最近は据えており、いかに顧客に役立つ製品であるか、という点でプロダクトエンジニアチームとの橋渡しをする役割をしています。

小川:私はお客様へのコンサルティング業務に携わりつづけており、お客様先でのニーズをヒアリングし、現場でDYNATREKのUIを作成していく業務が中心です。業務コンサルタントとプロダクトサポートの両方の仕事をしているイメージです。
―入社の理由は?
小川:お客さまの近くで仕事ができる点に惹かれました。以前の仕事では、要望を持ち帰って開発し、完成品を納めていたのですが、ダイナトレックでは、コンサルタントやCS職がお客さまの目の前で要望を聞き、開発チームに共有するスタイルを取っています。一方、エンジニアはフルリモートで働きつつ、必要に応じてお客さまのニーズに対応しています。できなかったことができるようになった瞬間、お客さまの顔がパッと明るくなって、喜んでくれるのを目の当たりにできるんです。本当にやりがいがあります。
櫻木:同感です。お客さまと一緒に走りながら開発できるのが、ダイナトレックで働く醍醐味ですね。
DYNATREKが金融機関の変革を強力にサポート
―DYNATREKはどのような企業のどういった課題を解決しますか?
佐伯:DYNATREKは、地方銀行、政府機関、大手通信会社、電力会社など、さまざまな業界で利用されており、今後は地方自治体への導入も拡大する計画です。現在、特に地方銀行での導入が進んでおり、地方銀行の約40%がDYNATREKを採用しています。銀行業界では、従来の融資サービスに加え、事業承継を含むM&Aなどのコンサルティングサービスの提供が増加しています。また、サービスの提供チャネルも従来の銀行窓口だけでなく、アプリやウェブサイトなどへと多様化しており、顧客との接点が広がっています。

しかし、このような多様なサービスとチャネルの増加により、商品やチャネルごとにシステムが分散され、顧客データを一元的に把握できないという課題が生じています。DYNATREKを導入することで、この分散されたデータを統合的に管理・分析することが可能となり、銀行は顧客の全体像を把握しやすくなります。これにより、顧客のニーズに基づいた最適なサービスを提供し、顧客本位の価値提供を強力にサポートすることができるようになります。
―DYNATREKを導入することでお客様の業務はどのように変化しますか?
佐伯:DYNATREKを導入することで、お客様の業務は次のように変化します。例えば、これまで融資だけを利用していたお客様のデータから、事業承継を検討している可能性が見つかれば、その情報を基にコンサルティングサービスを提案することが可能になります。また、資産相続に関する情報が得られれば、相続専門の担当者に繋ぐことができます。
このように、DYNATREKは異なる商品やサービス間でのクロスセルを支援します。具体的には、融資業務とコンサルティングサービスのクロスセルや、法人顧客と個人顧客の間でのクロスセルを実現することで、銀行が提供する価値を最大化し、顧客満足度を向上させることが可能です。

顧客の声を活かす開発プロセスと品質管理
ーダイナトレックでは、どのように顧客の声を反映しながら開発を進めているのですか?
佐伯:コンサルタントやCS職は週3日程度、お客さまのオフィスで課題を聞きながら対応しています。一方、エンジニアは基本的にフルリモートが可能で、必要に応じて出社するスタイルです。私自身はエンジニアですが、お客さまと直接対話することで開発の質を高めるため、任意で出社することがあります。
私たちは、あるべき姿やCSチームから上がってきた顧客の声を元にプロダクト責任者が開発すべき機能を策定した上で、エンジニア自らの意思または責任者の依頼によりタスク配分がされ、1週間ごとにMTGで振り返りをしながらアジャイルに開発を進めています。
マネジメントにも関わっているシニアメンバーによるコードレビューや実装方法の相談を行いながら、品質を高めよりよいものづくりをチーム全体で行っています。社内のテストチームのテストを経て早いときは毎週でデプロイを行い、頻度高く顧客の反応を見ながら開発を進めていきます。

実際に反映してみると、「もうちょっとこうしたい」「こんな機能もあったらいいな」というニーズがどんどん出てきます。ボタンの位置を変えたり、画面の文字を大きくしたりといった細かな改善も含め、それらをまたプロダクトに反映させていく。一見些細な改善でも、お客さまが毎日使うシステムですから効果が高いんです。
ダイナトレックの開発プロセスには、ビジネス側と開発メンバーが密接に連携する文化が根付いています。ビジネス側には、コンサルティングファーム出身者や金融業界での実務経験を持つメンバーが多く、それぞれが持つ専門知識を活かしてプロダクトの方向性を示しています。一方、開発メンバーには、IT企業やスタートアップで経験を積んだエンジニアが多く、技術選定やアジャイル開発の実践においても、自主性と柔軟性を発揮しています。
特に開発チームでは、「最新」よりも「最善」を重視する価値観が共有されており、顧客の課題を深掘りする姿勢が重要視されています。技術的な視点では、当然ですが開発の最前線のエンジニア自身が技術選定にも積極的に関与し、常にプロダクトの品質向上を目指す文化が根付いています。これにより、チーム全体が同じ方向を向きつつ、多様なバックグラウンドを活かした開発が可能となっています。

―DYNATREKは、カスタマイズして使うのが前提のサービスということでしょうか?
佐伯:いいえ、そうではありません。ある銀行の要望が、実は他の銀行でも課題だったり、これから課題になっていくということも多いんです。そこで、お客さまからの要望は、積極的にプロダクトそのものに取り込んでいきます。つまり、どの銀行もその機能を使えるように、プロダクト自体をどんどんバージョンアップしているんです。
―細かな要望も多いのではないでしょうか?
佐伯:全ての要望をそのまま取り入れるわけではありません。大切なのは、表面的な要望の裏にある、お客さまの本質的な課題を理解することです。少し踏み込んでヒアリングしていくと、細かい要望が10件くらいまとめて解決することもあります。
櫻木:例えば、「このような複雑なレイアウトな帳票を忠実に再現してほしい」という要望があったとして、「その帳票はどのような業務プロセスの中で使われるのですか?」「このようにシンプルにした方が、より皆様にとって使いやすいのではないでしょうか?と問いかけることもあります。お客さまに近い存在だからこそ「これってこうできるのでは」と想像が働く部分もあり、おそらくこの辺が、お客さまとの信頼関係やスムーズなプロダクト開発につながっているのだと思います。
小川:私もお客さまとの対話の中で、本当にやるべきことが明確になっていくことが多いと感じています。お客さまの中にもタスクの優先順位があります。「その要望って期中の目標にどう関係してくるのですか?」「中期経営計画に載っていることなんですか?」などと問いかけ、お客さま自身に全体戦略との整合性を考えていただきます。すると、枝葉が整理され、自然と優先順位の高いタスクだけが残っていきます。DYNATREKを活用したコンサルティングや現場でのUI開発では、技術力はもちろん、コミュニケーション能力が求められますね。
もっと顧客の近くに 金融機関同士のハブとなるコミュニティを運営
―これほど金融機関に支持されている理由は何でしょうか?
佐伯:ダイナトレックの製品は、もともと官公庁や経産省の貿易保険業務向けに開発されたシステムがベースになっています。つまり、政府機関が使うレベルの堅牢性がありながら、同時に自由にデータ分析ができるプラットフォームとして設計されているんです。そのバランスが、セキュリティを重視する金融機関に評価いただいているポイントです。
2012年に常陽銀行さま(茨城県水戸市)が金融機関で初めて導入し、横浜銀行さま(神奈川県横浜市)、千葉銀行さま(千葉県千葉市)、京都銀行さま(京都府京都市)など、全国に広がっていきました。これは地域金融機関特有のカルチャーも影響しています。どの銀行も共通の課題を抱えていて、「これは使える」となると業界全体で情報共有される傾向があるのです。
こうした情報共有の活性化に貢献しようと、私たちもDYNATREKのユーザー会議を作りました。年1-2回ほど主催行(幹事となる銀行)の会議室に集まり、DYNATREKの機能の使い方、開発の苦労まで、さまざまなテーマで語り合います。

2024年のユーザー会では、約25行、50名以上の金融機関ユーザーが全国から一堂に会し、自分たちの課題や取り組みを発表しました。そのつながりは、もはやDYNATREKという一サービスの域を超えて、金融機関同士が個別に連絡を取り合ってノウハウを共有し合うこともあるようです。こんなふうに気軽に情報交換できるようになったのは、非常に価値のあることだと思っています。
解決策は顧客の中にある
―最後に、ダイナトレックで働く面白さを教えてください。
小川:私は今46歳ですが、この年齢で現場で手を動かしながらマネジメントの仕事もできるのが面白いところです。前職のテレビ業界では、プロデューサーがいて、ディレクターがいて、カメラマンさんがいて、編集がいて……と、分業が基本で、ディレクション以上の人はマネジメントが中心になって、コンテンツづくりがしたくてもなかなかできなくなっていきます。私は、今のようにずっと現場でお客さまに寄り添って働けるのが、やっぱり一番いいなと思います。
櫻木:プロダクト開発の現場では、最新の言語、最新のフレームワークを常にキャッチアップしていくことがとても大切です。でも、忘れてはいけないことは、「ユーザーにとって最善である」ことがDYNATREKの良さであることです。解決策はいつも、お客さまの中にあります。
佐伯:金融機関のBIやデータ統合という領域は、本当に様々なDBMSやビッグデータに触れ、そこから価値を引き出していくというやりがいのある仕事です。そして、DYNATREKは金融機関の日々の業務を支える存在であるため、運用面でこれまで高い安定性を達成しており、それをこれからも持続していく必要があります。また、本年5月には米国サンフランシスコでの世界最大のFINTECHイベント「FINOVATE」でのピッチイベントに出場し、米国においても地方銀行では、いかにして自行が蓄積するデータを活用するかというてんで日本に共通する悩みがあることがわかりました。今私たちの軸足はもちろん日本にありますが、将来の海外展開なども見据えていきたいですね。
日本中に眠るビッグデータの価値をひきだしながら、その価値を金融機関の皆様に伝え、日本中を元気にしていく。そんな仕事に興味がある方は、ぜひ一緒にチャレンジしていってほしいです。
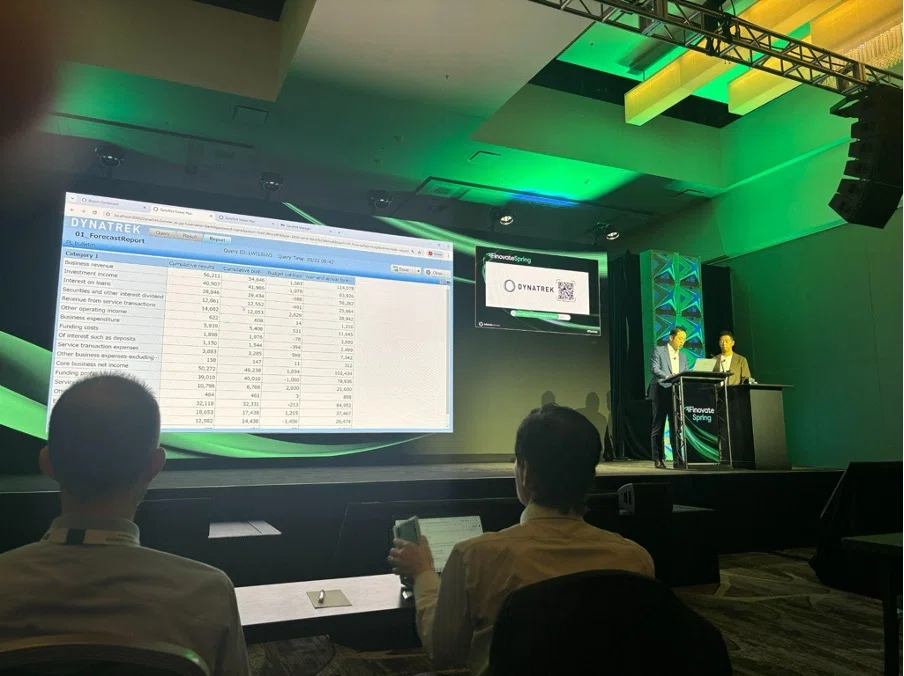
SHARE




